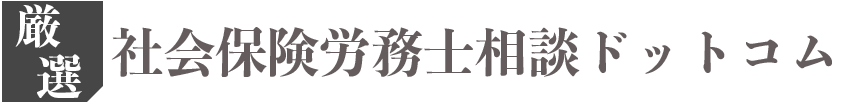就業規則の作成を社労士に依頼すると、自社特有の運用を適切に条文に落とし込めるので、従業員とのトラブルを未然に防ぎやすくなります。
とはいえ、就業規則の作成を0から依頼すると15万円~40万円程度かかるので、就業規則の作成を最初から任せるのか、ある程度自分で作った後に修正だけを依頼して費用を抑えるのか迷うところです。
この記事では、就業規則の作成や見直しをお考えの方に向けて以下6点をご紹介します。
- 就業規則を自分で作成する際の落とし穴
- 就業規則の作成・見直しを社労士(社会保険労務士)に依頼する7つのメリット
- 就業規則作成・見直しの社労士(社会保険労務士)費用相場
- 就業規則の作成・見直しに強い社労士(社会保険労務士)を選ぶポイント7つ
- 就業規則作成を社労士に依頼する前後の流れ
- 就業規則の作成を社労士以外に依頼する選択肢はあり得る?
トラブルにならないような就業規則を作るためにもぜひご参考ください。
就業規則を自分で作成する際の落とし穴
自社のことは経営者が一番詳しいので、就業規則を経営者自らが作るのも悪い選択ではありません。ただ、経営者の方は就業規則を作り慣れていなくて当然なので、困ることもたびたびあるかもしれません。
以下、経営者が自力で就業規則を作成した際に気をつけたいポイントをお伝えします。
記載するべき事項を載せられているのか調べるのが大変
就業規則には以下の3点を記載することになります。
- 絶対的必要記載事項:必ず記載しなければいけない事項
- 相対的必要記載事項:特定の制度を設けるなら記載しなければいけない事項
- 任意的記載事項:自由に記載できる事項
絶対的必要記載事項とは例えば、始業時刻や就業時刻、休日、賃金に関するルールなどです。
自力で就業規則を作成する場合に困ることの具体例は…
- 絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項を抜け漏れなく調べて記載しなければいけない
- 上記を記載した内容に問題がないか判断がつきにくいことがある
- 任意的記載事項に書いた方がいいことがあっても気づけないことがある
給与計算のような自社独自のルールを適切な文面に落とし込むのが大変
テンプレートや競合の就業規則を使った場合は、記載内容と自社の運用にズレがあって当然です。
- 具体的に書き換えなければいけない箇所に自分で気づかなければならない
- 書き換えた後の内容が適切かどうか、確信しにくい
労働基準法に違反しない内容になっているかわからない
給与の計算方法や労働時間のような決まりは企業によって異なる部分です。
テンプレートの記載ではややオーソドックスなので、自社の運用に沿うように変更される方もいるかもしれません。
最終的な記載内容が労働基準法に違反していないか確認したい場合は、社労士に確認してもらうと安心です。
不利な内容になっていても気づけない
テンプレートを使う際は内容をよく把握しないと金銭面で不利益を被ります。
例えば厚生労働省のモデル就業規則には、非正規社員でも正社員と同様の退職金が支払われる旨の記載があります。
これに気づかずに、アルバイトに退職金を支払わなければ給与未払いで請求をされても仕方がありません。
就業規則修正には労働者の合意が必要な場合も
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
労働契約法第9条
変更した内容が従業員にとって合理的であれば、就業規則の修正に従業員の同意は必要ありません。
ただ、上でお伝えしたようにアルバイトの退職金に関する記載を削除したような場合は従業員にとっては不利な変更になるので同意が必要になるかもしれません。
同意が必要なかったとしても、最終的に従業員に周知をしなければいけないので、立たなくてもいい波風が立つかもしれません。
最初に作った就業規則に不都合な内容が入っていた場合、修正するのが簡単ではないこともありえるので、できるだけ最初からトラブルが起きにくい就業規則を作りたいところです。
就業規則をどうしても自分で作成したい場合はレビューだけを依頼すると安心
少しでも外注費用を抑えたい場合、就業規則のレビューと手直しだけを社労士に依頼するのがいいかもしれません。就業規則の作成を0から依頼するよりも費用を抑えられます。

就業規則作成に月収30万円の人が7日間使ったとすると10万円分の人件費がかかったことになります。あまりに時間がかかりそうであれば、ぜひ社労士にお任せください。
就業規則の作成・見直しを社労士(社会保険労務士)に依頼する7つのメリット
以下、社労士に就業規則の作成や見直しを依頼するメリットをご紹介します。
- 助成金の受給も目指せる
- 就業規則に記入しなければいけない事項が漏れる心配がない
- 賃金や退職をめぐるトラブルを予防できる
- 法令改正の内容を踏まえて就業規則を作成できる
- 予期せぬ法令違反を防げる
- 不正があった場合に懲戒解雇できるようになる
- 本業に専念できる
助成金の受給も目指せる
就業規則の修正を依頼される方の中には、助成金を受給するために就業規則の依頼をされる方もいらっしゃいます。
助成金を受給するには、支給要件を満たすように労働環境と就業規則を修正しなければいけない場合があります。助成金は厚生労働省が労働環境を安定させるために企業に支給しているお金なので、人を何人か雇用していて長く働いてほしいと思っている企業であれば受給のチャンスがあるかもしれません。

社労士に依頼をしないと、受給できそうな助成金があってもなかなか気づけないものです。
就業規則に記入しなければいけない事項が漏れる心配がない
社労士であれば、上でお伝えした以下3点を抜け漏れなく記載できます。
- 絶対的必要記載事項:必ず記載しなければいけない事項
- 相対的必要記載事項:特定の制度を設けるなら記載しなければいけない事項
- 任意的記載事項:自由に記載できる事項
「書き忘れていることがあるのでは?」と心配しないで済みます。
賃金や退職をめぐるトラブルを予防できる
賃金や退職関係は、トラブルになった場合に請求される金額が高額になりがちです。
法令違反にならず、かつ経営者にとっても不利にならないような運用を考えたいところです。
例えば残業代の計算方法をどうするかというのも悩みどころです。
具体的な悩みどころは…
- 固定残業代にする場合は必ず就業規則に書かなければいけない
- 固定残業代にしない場合は正しい計算方法を調べて就業規則に記載しなければいけない
- 固定残業代にしない場合は、毎月間違えずに残業代を計算しなければいけない
- 就業規則の記載に不備があると未払い残業代を請求されることがある
- 就業規則の記載通りに残業代を計算しないと未払い残業代を請求されることがある
- 結局固定残業代を採用するべきかどうか迷う
社労士に相談することで、経営者を悩ませがちな賃金や退職に関する取り決めについて、自社にピッタリのルールを決められるかもしれません。適切な内容を就業規則に記載できるので、就業規則が原因で未払い賃金を請求されるリスクを少なくできます。
法令改正の内容を踏まえて就業規則を作成できる
法令改正は毎年されていて、普通に生活していれば変更があっても気づかないのが普通です。
テンプレートを使う懸念は、テンプレートが古くなっていて法令改正の内容が反映されていないことがある点です。
予期せぬ法令違反を防げる
自分で就業規則を作成した場合、「この内容で大丈夫だろうか」と一抹の不安が残る方もいらっしゃるでしょう。
社労士が就業規則を作成またはチェックすれば、万一法令違反に当たるような内容があった場合に指摘してもらえます。
法令違反とまではいかなくても、就業規則が原因のトラブルを未然に防ぎやすくなります。
不正があった場合に懲戒解雇できるようになる
就業規則に懲戒に関する取り決めを記入することは重要です。
就業規則に懲戒に関する記載がなければ、明らかに懲戒解雇が妥当だったとしても懲戒解雇が無効になることがあるためです。
仮に不当解雇が認められたとすると、懲戒解雇を言い渡した以降の賃金を支払わなければなりません。
就業規則を自分で作る場合は忘れずに懲戒について記載しましょう。
本業に専念できる
就業規則は経営者が作らなければいけないので、この間は本業に労力を割けません。
自力で就業規則を作成するのに時間がかかりそうであれば、社労士に依頼してしまうのもいいかもしれません。
就業規則作成・見直しの社労士(社会保険労務士)費用相場
以下、就業規則の作成や見直しを社労士に依頼した場合の費用相場をご紹介します。
就業規則作成の社労士費用|15万円~40万円
就業規則の作成を0から依頼した際の費用は15万円~40万円程度です。
金額に開きがある理由は、就業規則をどの程度作り込むかによって社労士の稼働時間が変わるためです。
時間がかかりそうなポイントは…
- 会社へのヒアリングに時間をかけている
- 独自の条文の作成に時間をかけている
- 完成した就業規則の内容の説明に時間をかけている
時間がかかっている分、会社の現状を反映していて安全性の高い就業規則を作成できます。
就業規則見直し・修正の社労士費用|3万円~20万円
就業規則の見直しや修正であれば、0から作成するよりも時間がかからないので3万円~20万円程度で依頼できます。
就業規則の作成・見直しに強い社労士(社会保険労務士)を選ぶポイント7つ
社労士を選ぶ際にみるべきポイントをお伝えします。
- 社労士が得意な業界を知る
- 実績を公表している
- 企業のことを考えたアドバイスをしてくれるか
- 実際に話してみての相性
- 料金体系・見積もりが明瞭か
- 就業規則の作成であれば遠方の社労士に依頼しても問題ない
- 複数の社労士に見積もりをもらう
社労士が得意な業界を知る
依頼予定の社労士の得意業界を聞きましょう。例えば、今まではWeb系企業の就業規則作成に多く携わってきた人に、急にヘアサロンの就業規則を作ってくれと言うよりは、ずっとヘアサロンや理容室で就業規則を作ってきたという人のほうが安心できますよね。
多様な業界の仕事をこなしてきた経験豊かな人がいい、というのはもちろんですが、そういう経験も知識も豊かな人に依頼するとなるとその分余計にコストがかかることもあります。であれば、自社の業界を得意分野とする社労士の方を選んだほうがいいですよね。
実績を公表している
就業規則以外にも、どんな仕事をしてきたのかサイトに記載されていれば軽く見ておきましょう。
サイトを持っていない社労士も多いので、気になる場合は初回問い合わせの際に合わせて聞くといいでしょう。
企業のことを考えたアドバイスをしてくれるか
就業規則を作成する際は、会社の実態を文面に落とし込む必要があります。そのため、大前提として話を聞いてくれそうな人を選ぶのが安心です。
現在の会社のルールに関して、リスクがあればきちんと伝えてくれそうな人を選べれば、今後のトラブルを防げます。
実際に話してみての相性
相談したいときに相談にのってもらえるか、知りたいことに明確に答えてくれるか、不安をきちんとヒアリングして対処してくれるかなどがポイントとなります。
話をしてみて「この人なら任せられそうだ」と感じる社労士をぜひ探してくださいね。
料金体系・見積もりが明瞭か
従業員の数や作業量によって就業規則作成の費用は異なるので、内訳や費用の理由を明確に提示してくれる相手を選びましょう。
金額に加えて具体的なサポートの範囲も比較したいところです。
就業規則の作成であれば遠方の社労士に依頼しても問題ない
就業規則の作成だけであれば、電話やweb会議だけで十分なので、お住まいの地域から離れた社労士に依頼しても大丈夫です。
複数の社労士に見積もりをもらう
サポートの範囲や最終的な金額はどうしても社労士によって異なってしまいます。
複数の社労士に見積もりを依頼した方が、ご自身にとってぴったりの社労士を見つけられます。
当サイトのフォームより、複数社労士への見積もりが可能です。就業規則作成を任せられる社労士をお探しの方はぜひご利用ください。
就業規則作成を社労士に依頼する前後の流れ
社労士を探してから就業規則を届出流までの流れをご説明します。
就業規則納品後は、労働基準監督署への届出や労働者への周知が必要なので忘れずにご対応ください。
初回問い合わせ
電話やフォームより初回の問い合わせをします。
依頼したい内容の概要や気になっているポイントをざっくりと伝えておくと、面談時に具体的な話をしやすくなります。
初回面談
就業規則を作成する上で気になっていることや費用について聞くと無難です。
残業代の計算方法や退職金のように、お金にまつわるルールに関して迷っていることがある場合はこの段階で伝えつつ、どのような提案をされるのか確認すると有益な時間を過ごせるかもしれません。
契約後の流れ(例:会社特有の事情についてどうやってすり合わせをするのか)についても気になることがあれば、初回面談以降のタイミングで確認しておくと安心です。
見積もりをもらう
料金表や見積もりをもらったりしましょう。
従業員の数や具体的な作業量、サポートの範囲によって就業規則作成の費用が変動するので、必ず複数の社労士を比較しましょう。
具体的なサポートの範囲と費用のバランスを見つつ、しっくりくる依頼先をお探しください。
ご契約
いい社労士が見つかったら契約をしましょう。
ヒアリング
会社特有の事情や就業規則に記入したいと、そのほか考えていることを伝えましょう。
気になる点があれば、箇条書きしておいて伝えるとなんらかのフィードバックを得られるのでおすすめです。
納品
納品された就業規則を確認し、気になる箇所があればこの段階ですり合わせをします。
労働者側への意見聴取
過半数加入労働組合または過半数労働者代表に意見聴取をします。この段階での同意は必ずしも必要ではありません。
就業規則を労働基準監督署に届け出る
管轄の労働基準監督署に届け出をします。従業員が10人以上いる場合は届け出が義務化されます。具体的な期限の定めはありませんが、なるはやで対応するのが無難です。
労働者に周知する
労働者への周知を怠ると周知義務違反で罰金が課せられたり、就業規則が無効になったりすることもありえるので、必ず以下の方法で周知しましょう。
- 見やすい場所に掲示する
- 従業員に書面で伝える(口頭のみではだめ)
- デジタル化していつでも従業員がアクセスできるようにする
- 全従業員に伝える
就業規則の作成を社労士以外に依頼する選択肢はあり得る?
最後に就業規則を社労士以外に依頼するのはどうなのか?という点を軽く補足します。
就業規則の作成は社労士の独占業務
就業規則の作成は社労士の独占業務であると社会保険労務士法第2条で定められているので、社労士以外への依頼はお勧めしません。
社労士であれば労働諸法の知識と実務経験があります。最新の法令改正を踏まえつつも現場の運用を反映した就業規則を作成できます。
就業規則を従業員に任せるのはだめ
就業規則は経営者が作成しなければなりません。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
引用元:労働基準法第89条
従業員に任せる選択肢はないので、消去法で自分で作成するか、社労士に依頼するかの二択になります。
まとめ
以上、就業規則の作成や見直しを社労士に依頼する際のポイントをお伝えしました。
社労士に依頼するメリットは、労働に関する紛争を未然に防げる点です。残業代未払いのような紛争が起きた場合、就業規則の内容が証拠になります。
記載が適切でなければ相手方の請求が認められるかもしれません。1人の請求が認められれば他の従業員にも正しく残業代が支払われなかったことになるので、複数人分の残業代を支払わなければならないこともあり得ます。
本業以外のところに労力やお金を割かずに済むよう、自社の運用にあった就業規則を作成しましょう。