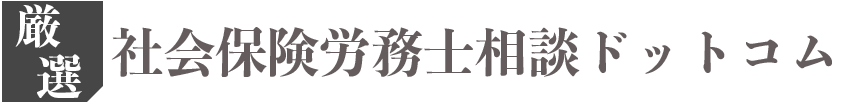社労士と顧問契約を検討するにあたって以下のような疑問はありませんか?
- 社労士と顧問契約をすると具体的に何をどこまで任せられるのか?
- 社労士との顧問契約が必要な場合と不要な場合の判断はどう考えればいいのか?
- 単発の依頼ではダメなのか?
- 社労士との顧問料の相場はいくらか?
- 社労士との顧問契約で失敗する理由は?
顧問社労士がいると、給与計算のようなルーチンワークを丸投げしたり、法令違反や従業員とのトラブルが発生しないような社内ルールを作れるので、安心して売上や利益に直結する業務に集中できます。
一方、「顧問契約をしたが、こちらから連絡をしないと何も提案してこない」というような社労士選びに失敗してしまうような方もいらっしゃいます。
この記事では、社労士との顧問契約に失敗しないために知っておきたいことを詳しめにお伝えします。ぜひ最後までご参考いただき、安心して仕事を任せられる社労士を見つけるヒントにしていただければ幸いです。
- 【超お得】顧問契約1年間無料キャンペーンのお知らせ ※クリックで詳細表示
- 「社労士選びで失敗したくない」
「割高な価格での顧問契約は避けたい」
そんな方には、50年以上の歴史を持つ社労士法人TSC(CACグループ)が提供する1年無料キャンペーンがぴったりです。
経営者からの要望が多い以下の業務を、一年無料で丸投げできます。
【1年間無料キャンペーン対象業務】
1.顧問契約
2.労務相談
3.勤怠管理システム
4.給与計算事務
5.労働保険事務
6.社会保険事務
7.助成金アドバイス
8.WEB明細システム
無料で社労士を試せるので、社労士と顧問契約をするとどうなるのか、雰囲気がわかります。不要な場合は途中で解約をすれば費用がかかりません。
CACグループは1965年創業で55000件以上の顧客契約数があります。50年以上企業をサポートしてきた実績と経験があるので、初めて顧問社労士を選ぶ方も安心して仕事を依頼できます。
詳細が気になった方は、以下をご確認ください。
社労士と顧問契約をした際に対応してもらえる業務の内容


・定期的に発生する手続きのまるなげ
・人事労務に関する相談
・社内ルールや就業規則の見直し
社労士会の調査によると、顧問社労士に依頼されることが多い業務は次のとおりです。

参考:全国社会保険労務士連合会|社労士のニーズに関する企業向け調査結果について
この調査から、具体的な手続きを外注したい企業と、継続的に相談をしたい企業が顧問契約をしていることがわかります。
では、社労士に相談・外注できる業務には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。詳しくご紹介します。
人事労務に関する相談・コンサルティング
人事労務にかかわる問題は経験や専門知識が必要なこともあり、経営陣だけでは法的に問題がないか判断できないこともあります。
顧問契約をしていると社内の状況を理解した上で社労士からの助言がもらえるので、自社特有の問題への答えを見つけられます。
人事労務コンサルを受ける場合、人材の採用や評価制度、就業規則のようなルールの最適化を目指すことになります。これらのルールを改善・最適化するには時間がかかるので顧問契約をするのが一般的です。
給与計算
給与計算も毎月行う業務としてなくてはならない内容ですね。しかし、給与計算も従業員が増えるにつれて負担が大きくなってくるため、できる限り外部に委託したい業務内容です。
労働や社会保険等に関する法律の専門家である社労士は、給与計算も得意とする分野です。社会保険等の手続きとも関係性が高い業務ですので、一緒に依頼した方がスムーズに進むと考えられます。
繰り返しますが、給与計算も顧問契約の範囲内で行ってくれるケースもあり得ます(特に従業員数が少ない場合)。顧問契約の前にはしっかり確認しておきましょう。
給与計算を社労士に依頼した場合、従業員が10人の場合2.5万円~5万円程度の費用で給与計算をすべて任せられます(従業員数が少なければもっと安い)。会社の規模にもよりますが、給与計算担当者の日給と給与計算ツールプラスアルファの費用で、[…]
助成金の申請
単発で済む場合もあれば顧問契約をした方がいい場合もあります。
顧問契約をした方がいい理由は次のとおりです。
- 助成金の申請から受給までは一定の期間がかかる
- 就業規則や社内のルールの変更などやるべきことが多い
- 助成金を毎年申請する場合は毎年手続きが必要
- 別の助成金を提案・申請してもらえることがある
単発と顧問契約のどちらがいいか判断したい場合は、複数の社労士に受給を目指す助成金の名称を伝えて、申請の準備から受給成功までのフローを確認しましょう。受給まで数ヶ月以上かかったり、毎年申請できたりする場合は顧問契約をするのが無難です。
費用は顧問料とは別料金になりますが、基本的には受け取れる助成金の一部となりますので、費用倒れする心配はありません。
社労士と顧問契約をしたのであれば、申請可能な助成金があるかどうかも相談してみると良いですね。
社労士に限らずいろんな職種の方が助成金、特に補助金の申請代行をしています。どの職種に代行を依頼するのがいいのか判断がつかない方も少なくないでしょう。結論からお伝えすると、助成金は社労士に、補助金は受給を目指す補助金に詳しい相[…]
労働保険・社会保険の手続き代行
法人が従業員を雇用するにあたって、社会保険、雇用保険、労災保険への加入と手続きは必須となります。数名程度の従業員であれば、なんとか自社内での手続きも可能ではありますが、従業員が増えていくにつれて負担も大きくなります。
社会保険等の手続き代行はその都度スポットで依頼することもできますが、従業員の入れ替わりは不定期で年間通して発生するため、社労士と顧問契約を結んでいつでも対処できるようにしておくことが多いです。
特にこれから成長を続けるような中小企業では、随時従業員を採用していくことでしょうから、なるべく早く社労士と顧問契約を結んでおくことが望ましいです。
従業員の研修
コンプライアンス遵守やパワハラ防止、人事労務関連の法令違反を防止するために従業員の研修が必要になることがあります。社内に詳しい方がいればその方が研修をされるのもいいですが、社労士に研修を任せることもできます。専門知識を0から勉強する必要もありませんし、最新の情報をもとに研修をしてもらえるので、社内でゼロから準備するよりも手軽に研修ができます。
就業規則・社内のルールの見直し
現在の社内のルールに法令違反の心配がないかリスクを確認してもらえます。採用や昇給に関するルールが将来的に変更になった場合も、法令違反になっていないかを確認してもらえます。
就業規則の作成や見直しは単発で依頼することも可能です。しかし、社内のルールは変化し続けるものです。顧問社労士がいると変更があった際にすぐに確認できます。
就業規則の作成を社労士に依頼すると、自社特有の運用を適切に条文に落とし込めるので、従業員とのトラブルを未然に防ぎやすくなります。とはいえ、就業規則の作成を0から依頼すると15万円~40万円程度かかるので、就業規則の作成を最初から任せ[…]
社労士との顧問契約が不要な(必須でない)業務の内容
以下の業務は単発での依頼も可能なので、顧問契約ありきではありません。ただし、以下の業務に付随して別の業務も依頼する場合や、定期的に依頼しそうな場合は顧問契約をした方がいいので状況に応じて契約内容をお考えください。
就業規則の作成・見直し
単に就業規則を作成したり見直ししたりすればいいだけであれば単発でも問題ありません。就業規則を作成・見直しをした上で、プラスアルファで相談や外注をしたい場合は顧問契約を検討するといいでしょう。
例えばキャリアアップ助成金を申請するためには社内の体制の構築や就業規則の見直しが必要になるので顧問契約をするのが無難です。
「会社の憲法」と呼ばれる就業規則は、労務管理において必要不可欠なものです。しかし一度作成したものを何年も放置し、「うちはきちんと就業規則を作成したから大丈夫!」と安心していないでしょうか。形骸化された就業規則では会社の実情を反映せず[…]
社会保険の算定基礎届
社会保険の算定基礎届とは、従業員の社会保険料を計算して申告する手続きのことです。年に1回しか発生しないので、今年の作業を任せたいだけで他の業務を依頼する必要がなければ単発での依頼で問題ありません。
労働保険の年度更新
こちらも保険料を計算して年に一度申告・納付する手続きなので、他に依頼したい業務がなければ単発で問題ありません。
社会保険・労働保険の新規適用
社会保険・労働保険に初めて加入する際に発生する手続きなので、この段階での顧問契約は必ずしも必要ありません。
労働契約書の作成
契約書のレビューは単発でも完結する業務なので継続的に採用について相談するニーズがなければ顧問契約は不要です。
労働条件の見直し
労働条件を変更する際は以下の2点に注意が必要です。
- 不利益変更になれば、従業員に説明が必要
- 労働基準法に違反していないか確かめた方がいいこともある
これらを確認するだけであれば単発の相談で問題ありません。
社内のルール・制度への相談・アドバイス
単に1回質問をしたいだけであれば顧問契約は不要です。
単発で相談しやすい内容は例えば…
- 健康診断・労働衛生に関するアドバイス
- 福利厚生制度に関するアドバイス
- 従業員の教育や研修のアドバイス
- 労働者の雇用形態に関するアドバイス
- 労働時間や休暇の取得に関するアドバイス
- 退職金や年金に関するアドバイス
社労士に単発で依頼できる業務や、単発でも依頼可能だが継続的な依頼を検討した方がいい業務について下記の記事でご説明しています。ご興味がある方は合わせてご参考ください。
社労士との顧問契約の必要性が高い5つのケース
ひとことでいうと、社労士と顧問契約をするといいのは継続的に相談や外注が発生するケースです。このケースに当てはまるのは例えば以下のような場合です。
初めて従業員を雇用するとき
初めて従業員を雇用するときは、やらなければいけない準備や手続きが特に多いので、顧問契約をするかどうかは経営者次第ですが、社労士の必要性が高くなります。
初めて人を雇用する際にやらなければいけないことは例えば…
- 雇用契約書の用意
- 就業規則の用意(従業員10人までは義務でない)
- 賃金規程の用意
- 勤怠管理・給与計算システムの用意
- 労働保険・社会保険への加入
これらの業務をすべて自力でやろうとすると売上や利益に直結する業務に時間を割けなくなるので、単発または顧問契約をして社労士に依頼をするといいでしょう。
上記全てを対応しようと思うと数ヶ月かかるので、上記の内容を依頼すると顧問契約を勧められることもあり得ます。年単位で社労士に相談・依頼するかどうか想定できない場合は3ヶ月更新で契約をするのもいいかと思います。
従業員とのトラブルを心配し始めたとき
人が少ない段階であれば、社内のルールを明確に決めたり、決めたことを就業規則に落とし込んだりいちいちしないかと思います。しかし人が増えてくるとルールが変わったり、実際の運用と就業規則の記載との間に乖離が生まれることがあります。特に給与や昇給に関するルールについては揉めた時に請求される金額が大きくなりがちなので気をつけるべきです。
「社内のルールや就業規則の内容はこれで大丈夫なのかな?」と気になり出した段階であれば、満足度高く社労士に仕事を依頼しやすいかと思います。
従業員が増えてきている(特に10名以上)
従業員数が増えている会社は、社内のリソースだけでは人事労務の対応が追い付かなくなってきている状況だと思います。
このまま自社内だけで対応しようとすると、本業への影響も出てきますし、万が一間違いがあった場合の影響も大きくなります。労働者とのトラブルも起こりやすくなってくると言えるでしょう。
実際には経営状況などにもよりますので一概には言えませんが、特に従業員数が10名以上になる場合には特に社労士への依頼を積極的にお考え下さい。というのも、上でも触れた就業規則作成の必要性が出てくることで、社労士依頼の必要性も高まるからです。
就業規則作成の依頼をきっかけに社労士と顧問契約を結ぶのも良いかと思います。社労士の人柄や働きぶりもある程度判断できますしね。
売上や利益に直結しない業務はアウトソーシングしたい
バックオフィス業務はできる限りアウトソーシング(外部委託)したいとお考えの経営者の方は、なるべく早くに社労士とも顧問契約をしておくことをおすすめします。
従業員が入退社する時の社会保険等の手続きは避けては通れない業務ですので、いずれ誰かがやらなくてはなりません。さらには、社労士には給与計算の依頼もできますので、本業と関係ない多くの業務を引き受けてくれるでしょう。
人事労務の相談相手がいない
起業して従業員を採用することになると、様々な法律が関わってきます。会社経営で関わることが多い法律のプロは、『税理士』『社労士』『弁護士』が多いのですが、当然事業を立ち上げたばかりの頃は専門家の相談相手もいないものです。
基本的には決算業務か労務関係での悩みが出てくることが多いでしょうが、労務関係の相談なら社労士が専門です。
メリットでもお伝えしたように、顧問契約を結ぶことで相談しやすい関係になり、さらには良きパートナーになれることも期待できます。起業したてで相談相手がいないという方は、相談相手としての顧問契約も検討して良いでしょう。
社労士との顧問契約が必要ない4つのケース
社労士に定期的に相談や外注をする予定がない場合は顧問契約は不要です。
顧問契約の必要性が低いケースをもう少し具体的にご説明します。
単発の相談・依頼で足りる場合
『社労士との顧問契約が不要な業務の内容』でご紹介したような業務は単発でも対応可能なので顧問契約は必須ではありません。
人を雇用しておらず、雇用の予定がない場合
社労士のサポートしている業務は、給与計算や社会保険の手続きなど人を雇用していないと発生しようがない業務です。
そのため、人を雇用する予定がなければ基本的に社労士との顧問契約は必要ありません。法人の場合は自分自身の役員報酬の計算が必要ですが、困ったときにスポットでミスがないか確認する程度で大丈夫でしょう。
税理士や企業に給与計算関連の業務を外注している場合
給与計算のように定期的に発生する業務を税理士や企業に既に外注している場合、必ずしも社労士との顧問契約は必要ありません。
この場合、社労士の独占業務を定期的に依頼したい訳でなければ顧問契約の必要はないでしょう。
社労士には独占業務があり、社労士以外の人物が独占業務を報酬を得て行った場合には、罰則も用意されています。社労士に依頼する側には罰則こそはありませんが、万が一社労士以外に独占業務を依頼した場合には、間違って処理されたり、行政への認可が[…]
顧問社労士がいたが問題が解決した場合
当初は顧問契約が妥当だったものの、問題が解決して顧問社労士が不要になるパターンです。よくあることなので、依頼したい業務がなくなった場合は感謝を伝えつつ契約を終了するのもいいでしょう。
社労士と顧問契約をする10のメリット
社労士との顧問契約するメリットについてもう少し詳しくご説明したいと思います。
効率的な業務フローを構築できる
人事労務に限らず、0から業務フローを構築したりツールや相談先を選定したり、マニュアルやルールを作成したりするのってものすごく大変だと思いませんか?
社労士に業務フローの構築を依頼すれば、試行錯誤しながら最適な業務フローを構築するまでの手間と費用をショートカットできます。
人事労務の部門がない場合は右も左もわからない状態なので、特に恩恵が大きいかと思います。人事労務の部門がすでにある場合は、複雑化した業務フローを見直して効率化を図れます。
労務担当者の退職リスクを気にしなくてよくなる
人事労務の専任の担当者を置くのはある程度企業の規模が大きくなってからかと思います。それまでは出来るだけ営業職のように売上に直結する職種の採用に力を入れたいところです。初期の段階では人事労務の担当者の人数が少なく、業務の進め方や進み具合が担当者一人に依存してしまいます。
担当者の人数が少ない場合、以下のようなリスクがあります。
- 担当者が退職すると業務が止まる
- 引き継ぎがされなかった場合、状況整理がすごく大変
- 労務の経験者を採用しなければならない
- 新しい担当者の教育が必要な場合もある
社労士に人事労務の手続きを外注する場合は上記のような社内担当者の退職に関するリスクはありません。さらに、人を1人雇用するよりも安上がりです。
給与計算や労働保険・社会保険手続きの計算ミスがなくなる
給与や保険料の計算ミスがあると従業員からの信頼を失いかねないので慎重に対応しなければなりません。社労士であれば基本的には計算ミスがありませんし、法令改正を踏まえて対応をしてくれるので間違いが起こりにくくなります。
労働基準監督署や年金事務所の調査への対応を任せられる
労働基準監督署からの調査に自力で対応するのは不可能ではないですがすごく不安になるのではないかと思います。
調査の際は必要書類の準備をした上で労基署の担当者の質問に答えなければいけません。顧問社労士であれば社内の状況をわかった上で適切に対応できます。
また、そもそも労基署に調査をされても問題ないような体制を構築できるので、安心感を持って事業に専念できます。
社内のリソースを確保できる
従業員数が増えて社員の入れ替わりが多く起きるにつれて人事労務の負担も増えてきます。最初は経営者や役員だけで対応していても、そのうち限界を迎えます。社労士に任せることで、業務負担は軽減でき、企画戦略や顧客対応などの本来やるべきご自身の業務に専念することができます。
コスト削減に繋がるケースもある
社労士ではなく、人事労務の担当者を採用するという方法も選択肢の1つです。これは従業員数や担当者の給与などケースバイケースになりますが、社労士と顧問契約を結んだ方が結果的に安く収まるケースも多いです。
例えば、担当者を採用するとなると1ヶ月で20~30万円ほどの給与は発生すると思いますが、社労士との顧問契約は、月数万円で収まるケースも多いです。それに合わせて追加で給与計算も依頼できます。
担当者の方にも、人事労務の仕事がない時には自社の業務を行ってもらうなどの方法はありますが、社労士に依頼すれば教育や引継ぎなどの手間もかかりません。
いずれにしてもケースバイケースで、社労士の方がお得に簡単に任せられることがあることは覚えておきましょう。
相談しやすい関係が作れる
顧問社労士との関係性が高まれば相談しやすい関係になり、いざという時に力強い味方になってくれます。
顧問契約している方が一般相談よりも優先的に相談を受けてくれますし、社労士の方もある程度の状況を把握しているので、相談からの助言も的確で素早いでしょう。
専門家から新しい情報を受け取れる
また、新たに法令が変更になったり利用できる助成金が増えるような場合には、社労士の方から新しい情報を教えてもらえることもあります。
事業主の方もある程度の情報にはアンテナを張っているとは思われますが、法令の細かい部分や助成金などの情報まで網羅できることは少ないですね。社労士は、労働や社会保険関係の法律、助成金申請のプロですので、情報も新しく正確です。
従業員からの信頼度も上がる
労務関係の整備が社労士によってきちんと行われていることで、従業員からの信頼も高まります。
意外と労働者は労務関係を気にしており、仮にいい加減な労務管理がされていると、後のトラブルにもなりますし、従業員の応募や離職率にも影響を及ぼしてくるでしょう。
最新の情報をもらえる
例えば法令改正に関する情報や助成金の情報など、自力ではなかなか気付くのが大変な情報をもらえます。
ただ、最新の情報を積極的に顧問先に伝えるかどうかは社労士のスタンスによります。「顧問料を払っているけど、こちらから連絡をしない限り連絡をしてこない」という不満もよくあるので契約前に最新の情報を定期的に発信することも契約の内容に入れておくのが無難です。最新の情報をもらいたい場合は、何に対しての最新の情報を欲しているのかを明確に伝えるのもポイントです。
最新の情報が必要な変更とは例えば…
- 労働基準法や労働契約法の変更のうち、従業員を雇用する経営者に関係のある変更
- 労働保険や社会保険に関する変更
- 自社が受給できそうな助成金の情報
社労士と顧問契約を結ぶ際の費用相場は2万円~17万円前後
以上が社労士に依頼できる主な業務内容ですが、社労士によっては顧問契約の範囲内で以下の業務を行ってくれたり、割安で引き受けてくれるケースもあります。
以下の業務の依頼も検討しているのであれば、顧問契約を結ぶ前にしっかり確認しておきましょう。
社労士の顧問料相場|旧報酬規程を参考にする事務所が多い
| 人 員 数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 |
| 報酬月額 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 | 63,000円 | 84,000円 | 105,000円 | 136,500円 | 168,000円 |
(注1) 人員数は、事業主、役員と全従業員の合計
(注2) 200人以上については別途協議
(注3) 建設業は、上記の金額に50%を加算
現在では廃止されましたが、社労士には報酬規程として以前まで報酬を一律で決めていました。旧報酬規程での顧問料の月額料金が上記の通りです。
最低21,000円からスタートして、従業員数が増えるにつれて報酬も上がる決まりです。今では報酬の設定も自由となりましたが、旧報酬規程を参考にしている社労士も多く、おおよそ上記の費用に近い料金設定にしている社労士がほとんどです。
実際には依頼を検討している社労士に細かく確認すべきなのですが、だいたいの相場については上記を参考にしてみてください。
内訳は基本料金+従業員数での追加料金
顧問料の内訳をもう少し詳しく説明すると、『月額基本料金』+『従業員数に応じた追加料金』となります。顧問契約の基本料金については、月額1~2万円に設定している社労士が多く、従業員数に応じた費用は以下の通りです。
- 4名以下:10,000円〜15,000円
- 5名〜9名以下:15,000円〜20,000円
- 10名〜19名以下:25,000円〜30,000円
- 20名〜29名以下:35,000円〜40,000円
- 30名以上:40,000円以上
具体的な社労士費用の相場については、以下のいずれの依頼の仕方をするかによって異なります。
- 相談・最終確認だけの顧問契約
- 相談+コンサルでの顧問契約
- 相談+手続き外注での顧問契約
- 単発依頼
社労士費用の詳細をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
社労士の顧問料相場は月額2万円~17万円程度です。金額に開きがある理由は、対応する業務の幅や量が異なるからです。相談だけの顧問契約であればもっと安く済みますし、人事労務のコンサルを含む場合はもっと高くなることもあります。[…]

契約内容によっては思ったよりも高くなるかもしれないな
金額が高くなるほど、契約内容や社労士選びのことなどで迷うかもしれません。そんな場合は、1年間無料キャンペーンを活用することで、1円も損をせずに社労士との顧問契約を試すのもいいかもしれません。
顧問契約を結ぶ際に信頼できる社労士を選ぶポイント
ここまでお読みいただいているということは、社労士との顧問契約も相当前向きな方でしょうから、最後に顧問社労士の選び方のポイントについてお伝えします。実際に社労士に相談・確認してみないと分からない部分も多いので、ある程度絞ったら直接社労士に相談してみることをおすすめします。
社労士への相談が初めてであれば、どうやって社労士を選べばいいのか判断基準が欲しい方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、社労士を比較する際のポイントを12点ご紹介します。もちろん社労士に何を期待するのかについては皆さまそれぞれ[…]
依頼したい内容に対する知識と経験
社労士への顧問契約は主に社会保険等の手続きと相談業務ですが、他にも依頼したい業務があれば、その業務に高い専門性と経験を持っている社労士を優先的に探しましょう。
大きく分けると、以下のような社労士がいますので、必要なニーズと一致した社労士を選んでいきましょう。
- 実務経験が豊富な社労士
- コンサル・アドバイスが得意な社労士
- 裁判外紛争解決手続き代理が行える特定社労士
業界への知識
社労士業務の種類には限りがありますが、依頼を引き受ける企業の種類は数多くありますね。社労士によっては、ある一定の業界に特化して依頼を引き受けているケースもあります。
そのような業界特価の社労士に依頼すれば、人事労務のアドバイスだけでなく、その業界に関する新たな動向にいち早く対応できることも期待できます。また、コンサル業務に力を入れている社労士も多くいるように、社労士が良き経営パートナーになってくれることも少なくありません。
相性の良さも重要
社労士選びで重要な要素に、社労士との相性があります。顧問契約ともなれば頻繫にある程度長くお付き合いする関係になりますので、人としての相性も重要なのです。
こればかりは、実際に社労士と話してみないことには分かりませんので、気になる社労士がいれば積極的に相談してみてください。
直接話す以前にも、
- 世代が近い/同性
- 業界への理解がある
- 経営者仲間からの推奨がある
このようなポイントである程度社労士を絞ることができます。
社労士との顧問契約に失敗したケース|対策・対処法
当サイトには社労士の切り替えのご相談をされるお客様もいらっしゃいます。個人情報保護のため具体的には書けないのですが、顧問社労士選びで失敗したと経営者が感じる理由のうちよくあるものを対策や対処法とセットでご紹介します。
毎月顧問料を払っているが特に提案がない(仕事をあまりしていない)
割と多い不満なので、これから顧問契約をされる企業の方はお気をつけください。
顧問契約をするということは人事労務の課題が継続的に発生してそれを改善していくことになるので、定期的にミーティングをして現状のすり合わせをするのが好ましいです。スプレッドシートなどに相談したいことや課題をメモしておけば建設的にミーティングができそうです。
社労士を選ぶ際は上記のように、ミーティングのような接点を持つ機会を提案してくるかどうか、ミーティングをするとしたらそこでは何をするのかを説明してくれるような社労士を選びたいところです。
契約前に見抜くのは難しいかもしれませんが、言われたことしかやらなさそうな人は避けるのが無難です。
相性が合わなかった
こちらも一緒に仕事をしてみないとわからないポイントなので、あわなければすぐ社労士を変えるしか対策のしようがなさそうです。契約前の段階であれば、1年契約ではなく3ヶ月契約で契約をしたり、契約期間の途中で解約ができるような内容で契約をしたりするといいでしょう。
- 経営者の方針と社労士の考え方にずれがあった
- 相談への回答が良くも悪くも正論ばかりである
- 経営者の立場に立ってもらえないと感じた
- 顧客目線でない
- 上から目線である
上記の中でも「経営者の立場に立ってもらえないと感じた」というお悩みは多いです。これは難しいポイントです。
似たような経験をしていたり、多くの経営者を相手に仕事をした経験をしていたりしないと経営者の立場に立つのは困難です。社労士を探す段階では、話をよく聞いてくれてこちらの意図をどの程度理解しているか確かめるくらいしかできなさそうです。いくつかの事務所と話をしてみると対応の違いがわかるので、最もこちらの意図を理解してくれて、かつ経験や実績が多い社労士を選ばれてはいかがでしょうか。
期待する働きをしてくれなかった
こちらが期待する対応と社労士の知識や経験が噛み合わなかったパターンです。
例えば…
- ITツールに疎く設定を任せられない
- レスが遅い
- 助成金などの情報提供がない
- 言われたことしかやらない
契約前の段階であれば、依頼したい業務内容を抜け漏れなく具体的に伝えて対応の可否を確認すればある程度スキルや経験のズレに気づくきっかけにはなります。相手にしてほしいことを具体的に言葉にして伝えたほうが早く解決する場合もあるかもしれません。
また、企業が成長すると人事労務の課題が変わったり、小規模な社労士事務所では業務量が方になったりすることもあります。このような場合は前向きな理由での社労士変更になりそうです。
社労士との顧問契約を解除する方法・手順
社労士との顧問契約を解除する際の流れをご説明します。
契約書を確認し、解約条項を確かめる
まずは契約書の解約条項を確認し、解約をする際の取り決めを確認しましょう。
「1~3ヶ月前に申し出ること」となっている場合が多いので、問題がなければ解約条項に従って解約を申し出ましょう。
この期間待てない理由がある場合は相手の合意を得られれば解約できます。ただ、引き継ぎの期間を踏まえるのであれば、1~3ヶ月程度の期間であれば待っても問題は少ないでしょう。
依頼している業務が完了したタイミングで解約を伝える
顧問契約が終了する以上、相手にとっては丁寧に仕事をする動機がなくなるので、丁寧に納品されるかどうかは相手の人間性に委ねられることになります。
中途半端な状態で納品されるのを防ぐためにも、今依頼している業務が納品された段階で解約を申し出るのが安全です。
書面で解約の通知をする
解約を伝える際は書面で通知しましょう。顧問契約解除通知書というような名前の書面を通知するといいでしょう。
引き継ぎのように細かい条件面についてもすり合わせたい場合は、契約解除合意書を作成し、具体的な条件を記入したうえで相手に送付するといいでしょう。
書面で通知することで契約の終了に関する証拠を残せるので、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
1~3ヶ月程度の引き継ぎ期間を設ける
現在お願いしている業務とその進捗を共有してもらい、引き継ぎをしましょう。1ヶ月あれば十分ですが、会社の規模が大きい場合は3ヶ月くらいで考えておくと安心です。
新しい社労士を探し、顧問契約をする
解約と並行して新しい社労士を探します。現在の社労士ではカバーしきれないポイントをうまく伝えられるよう、依頼したい業務をなるべく具体的に書き出しておくといいでしょう。
可能であれば、複数の社労士事務所と話した方が比較ができるので、社労士選びに失敗しにくいでしょう。
とはいえ複数の社労士に何度も問い合わせをするのは面倒かと思います。そんな場合は当サイトの一括見積もりをご利用ください。一括見積もりの場合、最初にメッセージを送れば複数の社労士に届くので、最初の文面については1度考えるだけで十分です。
見積もりを依頼する場合は具体的な業務を箇条書きし、依頼したい量や従業員の人数、見積もりを希望する旨をご記入いただくとスムーズです。以下をクリックし、フォームに必要事項を記入し、メッセージの送付をお願いいたします。
まとめ
社労士との顧問契約を検討している方に向けて、顧問契約をすると対応してもらえる業務の内容や、顧問社労士が必要なケース・必要ないケースについてご説明しました。
顧問契約をすると対応してくれる業務は…
- 給与計算・労働保険・社会保険のような定期的に発生する手続き
- 人事労務に関する相談
- 社内のルールの整備や見直し
顧問契約をするかどうかの判断基準は、ある業務を継続的に依頼するかどうかです。
社労士によって得意な業務や業界は異なるので、社労士選びに失敗しないためにも、複数の社労士に依頼したい業務内容を具体的に伝えて、提案や見積もりをしてもらいましょう。
一括見積もりを使うと、社労士を探す手間や、同じメッセージを何度も送る手間が省けます。同じメッセージを見た上で複数の社労士から提案や見積もりが届くので、自社の場合は顧問料がいくらが適切なのか判断しやすくなります。
無料でご利用いただけますので、社労士をお探しの方はぜひ以下のボタンをクリックし、一括見積もりをお試しください。
また、なるべく低予算で社労士に仕事を依頼したい場合は、TSC(CACグループ)の1年間無料キャンペーンを試してみるのもいいかもしれません。CACグループは50年以上の歴史を持つ老舗で、全国に拠点があります(全国対応)。各業界に精通した社労士が在籍していることもあり、社労士選びで失敗しにくいはずです。