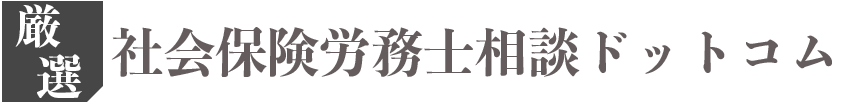社労士の顧問料相場は月額2万円~17万円程度です。
金額に開きがある理由は、対応する業務の幅や量が異なるからです。
相談だけの顧問契約であればもっと安く済みますし、人事労務のコンサルを含む場合はもっと高くなることもあります。
この記事では、社労士の顧問料と、各種手続きを単発で依頼した際の費用相場や内訳をできるだけ詳しくご紹介します。
社労士費用で失敗しないための参考にしていただければ幸いです。
- 【30秒でわかる記事要約】社労士費用で損しないためには?
- 1.社労士費用は次の3つの理由で変動するので、相見積もりをしないと自社にとっての相場はわからない
1.1.社労士費用はそれぞれの社労士事務所が自由に決められるので、金額や料金表のフォーマットが統一されていない(HPを見比べても結局トータルでいくらかかるのか、比較しにくい)
1.2.業務量によって費用が変動する。例えば、従業員人数が増えると給与計算のような業務の量が増えるので、その分費用が高くなる
1.3.顧問契約をする場合、次の契約の仕方がある。①相談だけ、②相談+コンサル、③相談+手続き外注。顧問料相場を比較する場合は、①〜③のどれを依頼したいか考えて相場を比較した方がいい
2.適切な金額で顧問契約や単発での依頼をするには
2.1.見積もり時に伝えるといいポイントは4つ①依頼したい業務の詳細、②単発か継続か(迷っている最中か)、③従業員人数、④その他希望や疑問点
2.2.顧問契約をする場合は、顧問料の範囲でどの業務をどこまで対応してくれるのかすり合わせてから契約をすると安全(毎月お金を受け取るだけで、最低限のことしかやらない、という不満がたまにある)
2.3.とはいえ、社労士に依頼をする際は、次のような点で迷うことがある。①どのような内容で契約をすれば損をしないか、②依頼する業務が増えると、雑務が減って楽にはなるが、意外と費用が高額になることもある、③人件費より安いとはいえ、顧問契約をすれば毎月の出費が増えるので誠実な社労士でないと安心できない
2.4.1年間無料キャンペーンを実施している社労士事務所がある。50年以上経営している老舗で、信頼と実績がある(全国対応)。企業からの要望が多かった7つの業務を無料キャンペーンの対象にしている。金銭的リスクなく社労士を試せるので、初めて依頼をする方や不安がある方にぴったり。
社会保険労務士(社労士)の顧問料相場は月額2万円~17万円
社労士の顧問料の相場は、従業員の人数によって変動することがあります。
社労士には「社会保険労務士会」が報酬を一律に決めていた時期がありました。旧報酬規定と言って、現在は廃止されている規定なのですが、今でもその規定を参考に報酬を決めている社労士事務所も多いようです。
下記が社会保険労務士の顧問報酬月額になります。
表:顧問報酬の月額費用(横にスクロールできます)
| 人 員 数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 |
| 報酬月額 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 | 63,000円 | 84,000円 | 105,000円 | 136,500円 | 168,000円 |
(注1) 人員数は、事業主、役員と全従業員の合計。
(注2) 200人以上については別途協議。
(注3) 建設業は、上記の金額に50%を加算。
ここでいう顧問報酬とは、社労士の業務のうち、次の表に掲げる8つの仕事、並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月単位で継続受託する場合に受ける報酬とされています。
| 法 律 | 備 考 |
| ①労働基準法 | 就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く |
| ②労働者災害補償保険法 | |
| ③雇用保険法 | 高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを 除く |
| ④労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 労働保険概算・確定保険料申告を除く |
| ⑤労働安全衛生法 | 許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く |
| ⑥健康保険法 | 健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く |
| ⑦厚生年金保険法 | 健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く |
| ⑧国民年金法 |
相談のみの顧問料相場は月額10,000円から40,000円
社労士が労災保険・雇用保険・社会保険などの手続き代行と、簡単な労働関連の法律相談などを行う場合は、相場として10,000円から40,000円程度の顧問料になるようです。
従業員の数に応じて変動しますが概ね下記のように変動していき、10名以下までは5,000円ずつ、10名以上になると10,000円刻みで上がっていくと思っておくと認識にそこまで大きな差は出ないかと思います。旧報酬規定と比べると、若干安く設定されているかと思います。
- 4名以下:10,000円〜15,000円
- 5名〜9名以下:15,000円〜20,000円
- 10名〜19名以下:25,000円〜30,000円
- 20名〜29名以下:35,000円〜40,000円
- 30名以上:40,000円以上
これに加えて、対面相談や電話・メール相談がトータル3時間までといった条件を設けている社労士事務所もありますし、『相談顧問料』と『手続き代行の顧問料』の2段階費用を設定している事務所もあり、何をどこまでお願いしたいかで正確な顧問料は変わってくることに留意が必要です。
労務系のコンサルティング顧問料
上記の基本顧問料は社労士事務所に業務をアウトソーシングした場合の顧問料ですので、労務コンサルになると少々顧問料は上がってきます。
| 労務コンサルティグ
| 内容 | 労務管理・労働時間短縮、就業規則、賃金規定の作成業務アドバイス など |
| 顧問料 | 50人未満:30,000円〜35,000円 | |
| 50人〜99人:40,000円〜50,000円 | ||
| 100人〜299人:50,000円〜60,000円 | ||
| 300人以上:70,000円以上 | ||
| 法務コンサルティング | 内容 | 登記や許認可に関するアドバイスや法律相談 など 顧問料:50,000円〜80,000円 |
| 顧問料 | 50人未満:30,000円〜35,000円 | |
| 50人〜99人:40,000円〜50,000円 | ||
| 100人〜299人:50,000円〜60,000円 | ||
| 300人以上:70,000円以上 | ||
| 給与計算コンサル | 内容 | 給与計算などの手続きや相談、コンサル など |
| 顧問料 | 50人未満:40,000円〜50,000円 | |
| 50人〜99人:50,000円〜70,000円 | ||
| 100人〜299人:70,000円〜80,000円 | ||
| 300人以上:100,000円以上 |
社会保険労務士(社労士)の報酬費用が事務所によって異なる理由
社労士によって、依頼をした際の費用はかなり異なります。その理由は、事務所が自由に料金体系を設定できるためです。
社労士費用の金額は、主に次の3つの要因によって変動します。
- 従業員の人数
- サポートの範囲
- 対応にかかった手間
従業員の人数が増えれば対応に手間がかかるため、その分費用がかかります。そのため、従業員の人数ごとに顧問契約の料金を決めている社労士事務所がweb 上でいくつか見られました。
さらに、顧問契約とひとえにいっても、カバーしている業務範囲は事務所によって異なるようです。例えば、給与計算のみ対応をしているケース、社会保険の手続きのみを代理しているケースなどがあり、カバーしている業務が多いほど高額になります。
また、手間がかかればその分人件費などがかさむので、コストが高くなります。就業規則を細かく設定したり、時間をかけてヒアリングをしてもらった際などに、費用が高騰しそうです。
1年無料で試せる社労士事務所を利用してみませんか?
ここまでお伝えした内容の要点は次の3つです
- 社労士費用の相場はおおむね2万円から17万円程度
- 電話やメールでの相談だけの顧問契約であればもっと安く、外注(給与計算、社会保険手続きなど)やコンサル(就業規則や人事制度の見直しによる組織改善)を頼むならもっと高いことも
- 従業員の人数、サポートにかかった時間・手間・人数が増えると顧問料が高くなる。どの程度外注するのが自社にとって最適なのか、悩みの種になることも

依頼内容の内訳次第で顧問料が大きく異なることがわかった。結局どんな内容で顧問契約をすればいいのか迷っている。
初めて社労士に外注する方であれば、お金の心配や不明点が多いはずです。そんな方は50年以上の運営実績を持つ社労士法人TSC(CACグループ)の1年間無料キャンペーンを活用すれば、1円も無駄な出費をせずに社労士を試せます。
【1年間無料キャンペーン対象業務】
- 労務相談
- 勤怠管理システム
- 給与計算
- 労働保険
- 社会保険
- 助成金アドバイス
- WEB明細システム
※ 経営者の皆様からのご要望が多かった業務を無料キャンペーンの対象にしています
給与計算や社会保険手続きから解放されたら、売上を上げるための業務にもっと時間を使えると思いませんか?
CACグループは1965年からやっており、これまでの顧客契約数は55,000件。責任を持って仕事をしてくれます。
1年無料キャンペーンの詳細が気になった方は、ぜひ以下をご確認ください。
【手続き別】単発で依頼した場合の社労士費用の相場
各種手続きを単発で社労士に依頼した際の費用相場をそれぞれご紹介します。
相談料1時間あたりの社労士費用相場
| 相談料 | 5,000円~1万円/1時間 |
| 依頼を検討している方の初回相談(面談) | 無料 |
助成金の社労士費用相場
| 助成金の申請 | 着手金0円 報酬金20%~ |
※別途就業規則の作成・修正が必要になることも。就業規則の費用の表をご参考ください。
助成金をもらいたいけれども、自分で申請するのと社会保険労務士に依頼するのとでは、どちらの方が良いのかな?と悩む人もいるでしょう。私は人事・労務担当者ですが、過去に自分で助成金申請をしたことがあります。結果的に受給には成功した[…]
就業規則作成・修正の社労士費用相場
| 就業規則作成 | 50,000~150,000円 |
| 就業規則修正 | 20,000~30,000円 |
| 諸規定作成 | 30,000~50,000円 |
就業規則の作成を社労士に依頼すると、自社特有の運用を適切に条文に落とし込めるので、従業員とのトラブルを未然に防ぎやすくなります。とはいえ、就業規則の作成を0から依頼すると15万円~40万円程度かかるので、就業規則の作成を最初から任せ[…]
給与計算の社労士費用相場
| 給与計算 | 従業員数 | 月額 |
| 基本料金 | 10,000~30,000円 + 従業員1名あたり500円~1,000円 | |
| 従業員数5~9人 | +5,000円~ | |
| 従業員数10~19人 | +10,000円~30,000円 | |
| 従業員数20~29人 | +20,000円~4,5000円 | |
| 従業員数30~49人 | +40,000円~70,000円 | |
| 従業員数50人~ | +50,000円~80,000円 |
給与計算を社労士に依頼した場合、従業員が10人の場合2.5万円~5万円程度の費用で給与計算をすべて任せられます(従業員数が少なければもっと安い)。会社の規模にもよりますが、給与計算担当者の日給と給与計算ツールプラスアルファの費用で、[…]
労働保険・社会保険の社労士費用相場
| 労働保険年度更新 | 3万円~10万円 ※人数により変動 |
| 社会保険算定基礎届 | |
| 社会保険・労働保険の新規適用 | 3万円~5万円 |
| 社会保険・労働保険の資格取得 | 1万円~2万円/1件 |
| 社会保険・労働保険の資格喪失 | 5,000円~1万円/1件 |
障害者年金申請の社労士費用
| 障害者年金申請 | 初回相談:無料 着手金:1~3万円 成功報酬:以下のうち高い方 年金額の2ヶ月分 または 遡及された場合は遡及分も含めた初回入金額の10~20% |
社労士費用一括見積もりで、お得な社労士を見つけましょう


ネットで調べるだけでは、社労士に依頼するといくらかかるのか、ざっくりとしか知れません。
社労士費用がトータルでいくらかかるのかわかりにくい原因は、次の3点が会社や社労士によって違うからです。
- 社労士事務所によって料金が違う
- 依頼したい業務の内容と数によって費用が変わる
- 従業員人数によって費用が変わることがある
社労士費用の相場を知るには、依頼したい業務の種類と量を伝えて複数事務所から見積もりをもらうのが近道です。

と思った方は、当サイトの一括見積もりをご利用ください。具体的なご依頼内容と見積もりを希望する旨をご入力いただければ、複数の社労士から見積もりを得られます。同一の業務内容に対して複数の見積もりと提案が届きます。
一括見積もりを使うメリットは…
- 相場以上の費用を支払ってしまう心配をしなくて済む。
- 複数の社労士に別々に何回もメッセージを入力して送信しなくてもいい
- 社労士の提案や対応を比較できる
以下をクリックし、具体的な業務内容と必要事項を記入し、社労士を探すをクリックしてください。
社会保険労務士(社労士)は月額顧問料の範囲内でどれだけの業務をしてくれるのか?
では、顧問社労士に支払う月額顧問料の範囲内でどの程度の仕事をしてもらえるのでしょうか?こちらに関して、社会保険労務士会が平成28年に実施したアンケートによれば、企業が顧問社労士に依頼する業務は「手続業務:72.7%」「相談業務:74.7%」という答えになっています。

参考:全国社会保険労務士連合会|社労士のニーズに関する企業向け調査結果について
手続きや簡単な法律相談・アドバイスは顧問料の範囲内とみてよい
この調査結果からでは顧問料の範囲内がどこまでか?という問いに対する正確な回答にはなりませんでしたが、
- 入退社に伴う各保険の取得手続
- 労働保険の更新手続
- 社会保険算定基礎届
- 社会保険賞与支払届 など
基本的な手続きの代行と、月に数時間程度の簡単な法律相談であれば、企業の利用率を鑑みるに、ほとんどの社労士が弁護士が顧問料の範囲内で対応していると言えそうです。
もちろん、顧問料と同様にどの程度の業務までを顧問料に含むかは個別の社労士事務所でことなります。
どこまで対応してくれるかは社労士次第
顧問契約とはいえ、相場以下の顧問料を設定している場合、何か手続き以外のことを相談すれば別途費用が発生するケースもあるでしょう。そのため、お願いしようと思っておる社労士に、相談も含まれるのか、何時間まで対応してくれるのかもチェックしましょう。単純に顧問料の安さだけで顧問社労士を選ぶべきではありません。
顧問弁護士と顧問契約を結ぶにあたっては、月々の顧問料にどこまでの業務が含まれるかをきちんと確認しておくことが大切です。
そのうえで、たとえば契約書の作成や法的トラブル時の対応など、顧問料の範囲内となる業務の扱いについてもあらかじめ説明を受け、納得した後に顧問契約書を交わしましょう。
社会保険労務士(社労士)費用をできるだけ抑える4つのポイント
安い事務所に依頼するのが合理的なのでしょうか。金額以外に社労士を決める基準はあるのでしょうか。
ここでは、上記の内容を踏まえ、社労士選びで損をしないためのポイントを4つお伝えします。
具体的にどの業務をアウトソーシングしたいのか定義する
現在社内で抱えている業務のうち、具体的にどの業務を外部に発注するのか定義するといいかもしれません。
顧問契約を結んだ場合は幅広いサポートを受けられる場合もありますが、依頼する必要のない業務がサポート内容に入っていた場合、金銭的に損をしてしまうことがありえます。
給与計算を外注したいのであれば、給与計算のみで顧問契約を。労働保険・社会保険の手続きを代理してもらいたいのであれば、労働保険・社会保険の代理のみで顧問契約を結ぶのが、費用の節約になるかと思います。
サポートの範囲を確認すために、無料面談を活用する
顧問契約を結んだ際に、具体的にどんなサポートを受けられるのか聞いてみましょう。現段階で必要のないサポートが含まれていた場合は、費用を交渉するか、他の事務所を検討するかの2択になるかと思います。
依頼前に費用を見積もってもらう
就業規則の作成など、依頼者のニーズによって工数が変わるような案件の場合は、提示される見積もり費用が社労士によって異なってくるかと思います。
社労士の側からしても、こうした案件は目安の費用をHPに掲載するしかないので、遠慮せずに見積もりを出してもらいましょう。
2~3事務所に見積もりを出してもらう
手間はかかるものの、複数事務所に見積もりを出してもらった方が大まかな相場感もわかりますし、自社に合うような提案をしてくれる社労士にめぐり合いやすくなるかと思います。
そのため、時間が許すのであれば、2~3社とコンタクトをとってから依頼を決めるといいでしょう。
当サイトより、複数の社労士に一括で見積もり依頼ができます。社労士費用を比較したい方はぜひご利用ください。
優秀な社会保険労務士(社労士)の選び方|比較すべき3つのポイント
顧問料と一括りにまとめてしまうと一体いくらになるのかわかりにくいですが、一つ一つ何をお願いするのかを明確にしていけば社労士の顧問料は決して高い費用ではないと思います。
入退職の手続き、雇用保険の申請、社会保険関係の手続きや申請は素人では難しいですし、就業規則の作成や給与計算も間違えたら大変なことになります。また、法律改正情報などは「知らなかった」では済まされません。
「会社には人事がいるから大丈夫」と思って方も多いですが、人を採用することと、採用したかたの手続きをスムーズに進めることはまた別の話ですし、社内の契約周りがしっかりしていないと早期退職の原因になります。
特に法律の改正はかなり頻繁に起きていることをご存知でしょうか?休日の規定や有給休暇の取得義務、実はあまり知られていない助成金の存在など、人事労務のプロである社労士と顧問契約することで「損をしない」というのが一番のメリットです。
だからこそ、ちゃんとした社労士を選ぶことで、余計なトラブルに対応するコストもなくなるのです。
相談内容にあった経験を積んでいるか
社労士の業務範囲は幅広いため、社労士ごとに得手不得手があります。
社労士の業務を大まかに分けると…
- 労働分野(労務管理・手続き代理・コンサルティング)
- 社会保険分野(医療・年金・介護)
依頼したい内容を明確に把握した上で、依頼内容とマッチする経験を積んでいる社労士を探しましょう。
まずはHPを確認して、どんな業務を取り扱っているのか、顧問契約で何をサポートしているのかをみるとその社労士の得意分野が見えてくるかもしれません。
めぼしい社労士事務所を見つけたら、電話や面談相談で具体的な質問をいくつかしてみて、満足のいく回答が返ってくるかどうか確認してみると、依頼後のギャップが少なくなるかと思います。
社労士事務所が強みにしている業界を調べる
社会保険労務士もこれまで扱ってきた業務、顧問として関わってきた企業の風土・業界によって専門性に磨きが違います。専門にしている分野とは別に、その社労士がどの業界・業種に精通しているのかを知ることも、選択の基準としては重要です。その社労士が得意とする業種は何なのか、社労士選びで有効であるとも言えます。
担当社労士との相性の良さも大事
考え方や馬が合うかといったポイントも、長く付き合うのであれば気にしたほうがいいかもしれません。企業側の考え方をよく理解していない社労士に就業規則作成の代理などをお願いすると、極端な話依頼者の意図とは異なる成果物が出来上がることもありえるかもしれません。
社労士への相談が初めてであれば、どうやって社労士を選べばいいのか判断基準が欲しい方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、社労士を比較する際のポイントを12点ご紹介します。もちろん社労士に何を期待するのかについては皆さまそれぞれ[…]
まとめ
- 顧問料の月額相場はおおむね月2万円~17万円程度
- コンサルや外注も依頼する場合はその分費用が高くなる
- 依頼したい業務の内容、量(従業員数など)、期間は企業によって異なるので、最終的には相見積もりをしないと自社にとっての相場はわからない
- 社労士に依頼したい業務を明確にしたうえで顧問契約をしないと、不満につながりやすい(例:助成金の提案をしてこないなど)
- 誠実さ、業務経験、業界知識などがある社労士を選ぶことで、費用対効果を高められる
- 最終的に、面談や依頼をしてみないと自社にあった社労士なのか判断しにくい。50年の歴史をもつTSC(CACグループ)が経営者からの希望が多かった7つの業務を1年間無料で提供しているので、お金を無駄にすることなく手続きを丸投げする快適さを体験できる